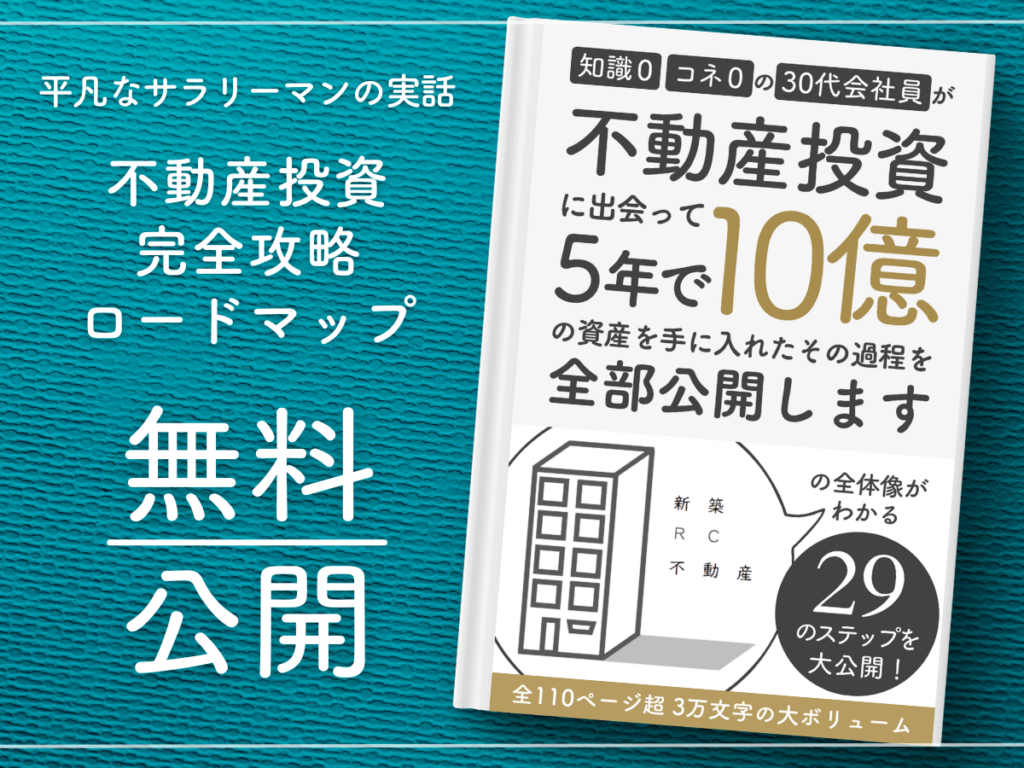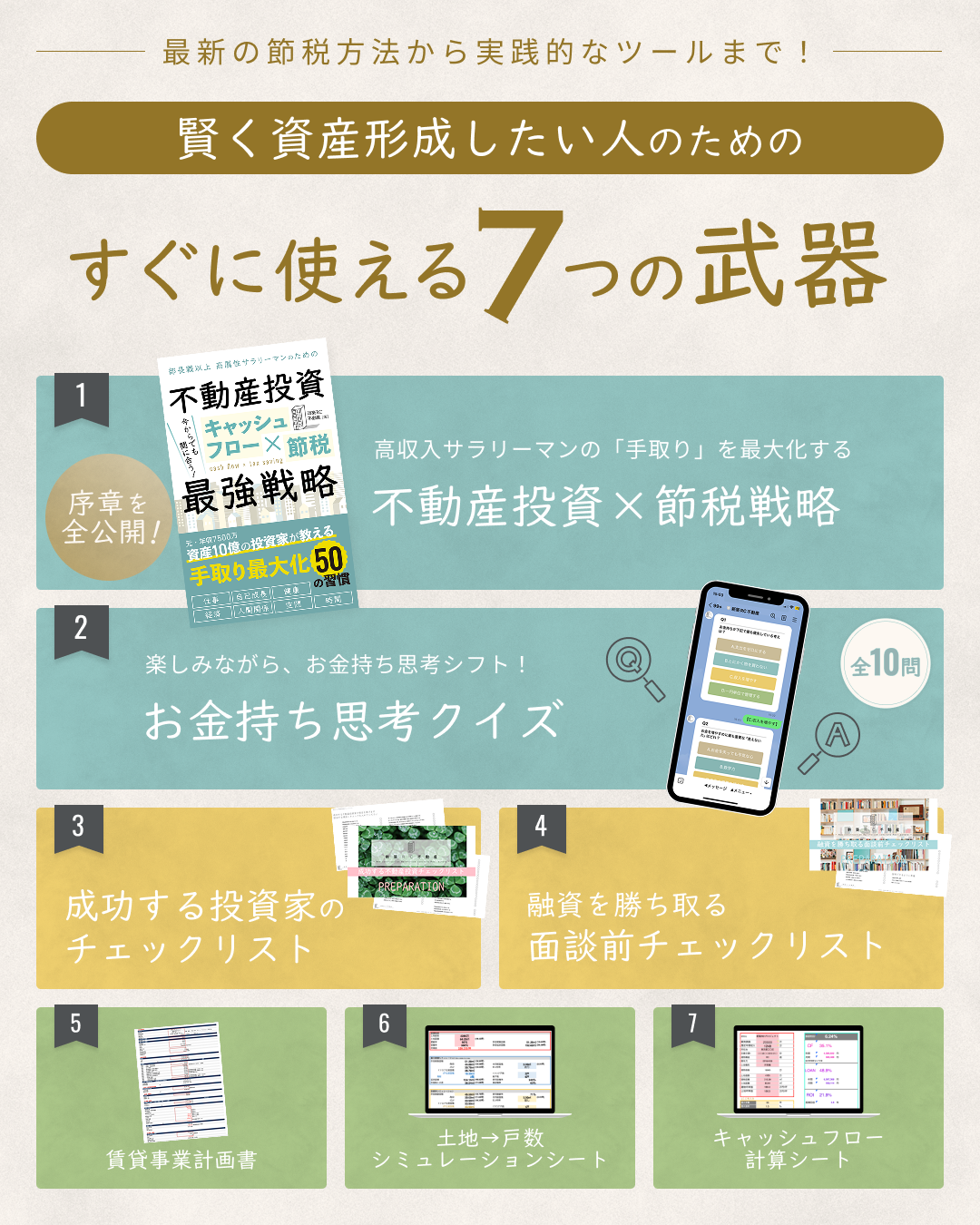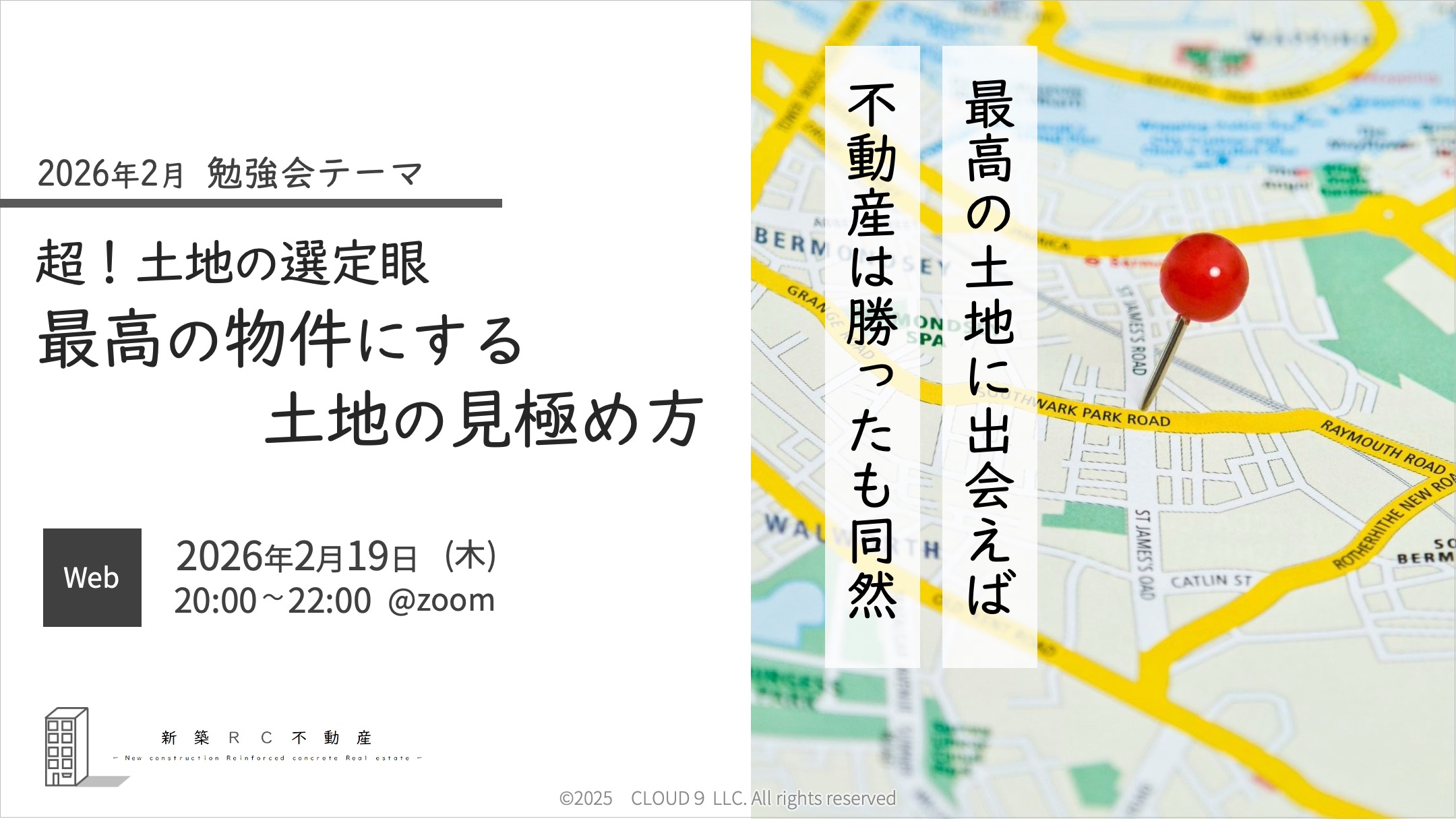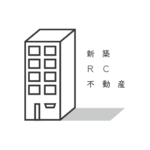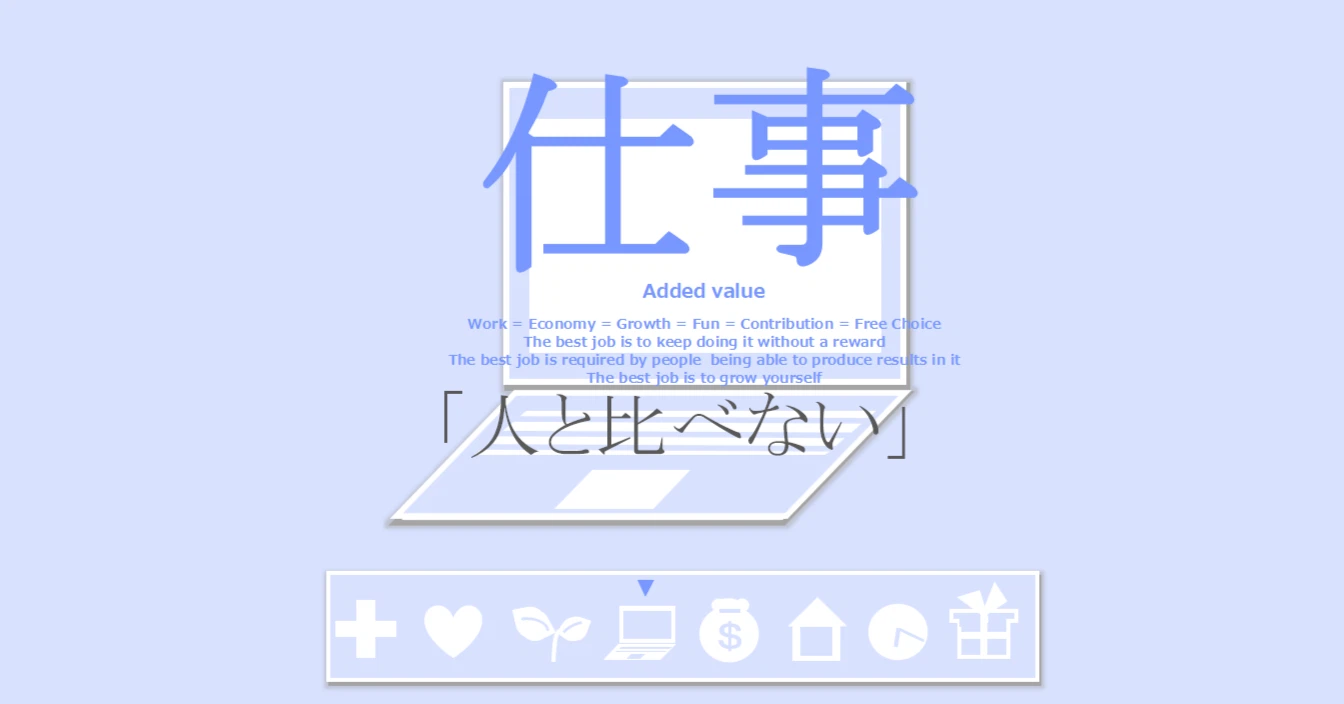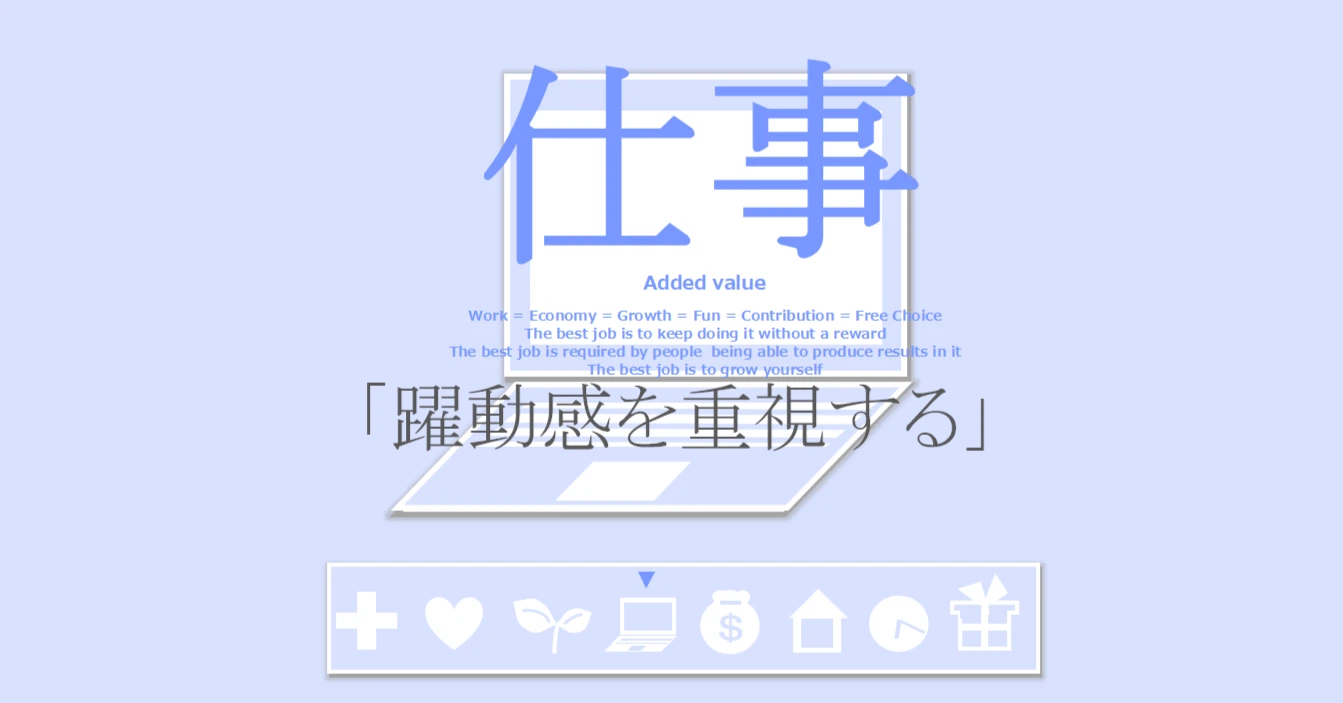仕事の習慣「できない理由を聞かない」

概要
仕事上で、同じチームのメンバーや
部下とコミュニケーションを図る中で、
上手くいかなかった時、
出来ない・出来なかった等の
失敗した理由を聞かないという
内容です。
なぜ始めたか
人を育成するということが、
仕事の中の大きな役割の一つとして
あると思います。
ある程度、一つの職場で経験を積んだり、
技能が上がってくると、
後任を育てるということになると思います。
育成論というのは、色々あると思います。
その中で、わたし自身が
非常に大事にしていることは、
できるだけ得意なことや好きなこと、
出来ることを徹底的に伸ばす
ということです。
なぜなら、その得意なことが
異なる人達が合わさることによって、
組織として強固となるというのが、
重要な状況だと思っているからです。
これは、答えではなく、
わたしの考え方ですので、
人に押し付けるつもりはないのですが、
対極の意見として、
苦手を克服し、オールラウンダ―の育成をする
という考え方もあると思います。
自分自身がそうだったのですが、
苦手なところを頑張る労力に
エネルギーを使うより、
その分を得意なことに注ぎ込み、
徹底的に伸ばして、
人が真似できないレベルにする方が、
その道のりも楽しいですし、
成長も感じられるし、
自分だけの技能も身につくため、
大事なんじゃないかなと思っています。
自分が指導する立場として、
育成する側の人が、当然、
思い通りにいかないこともあると思います。
ただ、重要な人間関係の原則として、
他人をコントロールすることは
できないというものがあるので、
どれだけ良い育成内容を実行したところで、
それ通りに、人は育たないわけです。
思い入れが強ければ強いほど、
そこに対して強く関わりすぎてしまう
と思うのですが、
その中でも特に、わたし自身、
やられてすごく嫌だった・
辛かったなということもありますし、
自分は、これはしたくないなと思うものが、
「詰問」と言われるものです。
簡単に言うと、
「詰める」
という言葉になるのですが。
この「詰める」ということを、
言葉の内容と言っている時の態度の
二方面から見て、
「詰問」になっているかどうかが
判断される思います。
よくあるのは、強い口調で、感情をぶつけて、
相手を追い詰めるような持っていき方をする方法。
これは、最近、極力やめていきましょう
という風潮がある方法だと思います。
その裏側で、もう一つ陥りがちな詰問というのが、
言葉遣い自体は丁寧で、激しい言葉遣いを
していなくても、
結果的に、相手を追い詰めてしまっている
というケースです。
これは、言う側・言われる側の
人間関係であったり、
受け取る側の心理的な部分が
多分に影響するのですが、
わたしが中でも気にしているのは、
出来なかったことや失敗に
フォーカスする関わり方です。
「なんでできなかったんですか?」と
仮に柔らかい口調で聞いたとしても、
出来なかったことに
フォーカスが当たっていることで、
相手への心理的な負担が大きいんじゃないかな
というふうに思うわけです。
出来なかった理由を答える時、
ある意味、正解はないと思うんですね。
正解がないというのは、
良い方向に転じないということです。
仮に、出来なかった理由を並べ立てたとしても、
結局、出来ていない結果があるわけですから、
「それって言い訳だよね」と言われてしまえば、
ぐうの音も出ないわけです。
かといって、何も答えられなかったら、
「出来ない理由を見つけられてもいないのか」と、
次の改善すらも思いつかないのかと責め、
追い詰めていくことは、簡単なわけです。
簡単ですし、指導する側からすると、
更に詰める方向へ持っていきやすくなってしまう
のではないかなというふうに思います。
なので、わたし自身も、
何か物事が上手くいかなかった時に、
そこにフォーカスを当てるということ自体を
あまりしたくないなというふうに思うんです。
よくある言い方ですが、
「じゃあ、何が出来れば上手くいったのか」
とか、そういう聞き方をする方が良い
と言われるのですが、
そこもある種、指導する側が答えを持っていて、
それを言わせたいという誘導的なものではなくて、
本当にフラットな信頼関係がある空気感の中で、
改めてフラットに考えて、
次、どのような手が考えられるかを
一緒に考えてみようというふうに
持っていけるかどうか。
これが、非常に大事な
育成のコミュニケーションではないかと思って
心掛けています。
効果
- 育成において、上下関係を意識せずに本音が語り合える人間関係が作れる。
- 長所を、より伸ばす方向に育成することができる。
- 相手が本当に思っていることを引き出しやすくなる。
人は誰でも
得意なことと
不得意なことがあって
それぞれ異なる
良い所だけを
全員で集めて
強い良い組織にしていくことが
理想